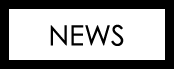

母校の玉名高陸上部の生徒たちと笑顔で交流する金栗四三。1965年ごろの撮影とみられる。(玉名市立歴史博物館提供)
日本人で初めて五輪に出場したマラソンの金栗四三(1891~1983)には、ドラマチックな記録がある。
「54年8カ月6日5時間32分20秒3」。1912(明治45)年開催のストックホルム五輪マラソン競技で、ゴールするまでにかかった時間だ。もちろん公式記録ではないが、ひと昔前の人の一生にも相当する長いタイムは、日本の陸上競技の発展に尽くした、いちずな人生を象徴している。
玉名で生まれ育ち、幼少の頃から勝ち気な頑張り屋だったという。教師を目指して東京高等師範学校(現筑波大)に進み、マラソンランナーの才能が開花。20歳の時、ストックホルム五輪の国内予選で出した2時間32分45秒(当時は約40・2キロ)を皮切りに、非公認ながら当時の世界記録を上回るタイムを生涯に3度打ち出している。
だが、勇んで乗り込んだストックホルム大会は猛暑のレースとなり、中盤で意識を喪失。日本五輪史の最初の1ページに「途中棄権」の文字を刻む結果となった。再起を期した4年後のベルリン大会は第1次世界大戦のため中止。8年後のアントワープは16位、33歳で臨んだ最後のパリは再び途中棄権に終わった。
世界と戦える実力を持ちながら、ひのき舞台で挫折を3度味わった悲運のランナー。だが、繰り返す失意の中でも、四三がマラソンへの情熱を失うことはなかった。
明治~昭和期に活躍し、「日本マラソンの父」と称される金栗四三が、2019年のNHK大河ドラマ「いだてん~東京オリムピック噺[ばなし]」に主人公として登場する。20日で生誕から126年。生涯に25万キロを走ったとされる偉大なアスリートの軌跡をシリーズでたどる。(蔵原博康、前田晃志、木村馨一)
2017年08月20日(日)付 熊本日日新聞朝刊掲載

1912年のストックホルム五輪出場後、ユニホーム姿で記念撮影する金栗四三(玉名市立歴史博物館提供)
「日本人は体力が不足し、技量も未熟だ。粉骨砕身して技を磨き、必ず雪辱を期す」
初出場したストックホルム五輪のマラソンで無念の途中棄権となった金栗四三。その直後に書きつづった決意の通り、やがて斬新な練習法や選手育成のための競技会をいくつも生み出し、黎明[れいめい]期にあった日本の陸上競技を育て上げていく。
その代表例が、今年で誕生100年になる日本発祥の「駅伝」だ。1917(大正6)年に京都-東京間で開催された最初の東海道五十三次駅伝競走の企画に参加し、選手としても出場。その3年後に四三らの提案で始まった箱根駅伝は、やがて正月の風物詩として定着した。
「五輪に初めて挑んだ頃の日本には、まだ近代スポーツが根付いておらず、マラソンの先駆者もいなかった。金栗さんは何もないところから研究と努力を重ね、必死で未知の世界を切り開いていった」
四三に関する著書があり、長く交流を続けた元熊本陸上競技協会長の長谷川孝道氏(86)=熊本市=は、その功績と人間的魅力に賛辞を惜しまない。
時は移り67(昭和42)年3月、郷里玉名で後進の育成などに当たっていた四三は、招待されて再びストックホルムを訪れた。五輪開催55周年を記念する国際親善イベント。マラソンの途中で力尽き、競技場に戻らなかったことから「消えた日本人」として有名だった。
大会当時と同じ競技場に立ち、コート姿のままトラックを数十メートル走ってゴール。半世紀を超えたドラマの終幕を、現地の新聞もユーモアを交えて報じた。当時75歳。帰国した四三は笑顔で語った。「私はランニング姿で本格的に走るつもりだったが、向こうの人が心配して長くは走らせてくれなかった」。ランナーとしての生き様を貫いた人生だった。(蔵原博康)

金栗四三の経歴
2017年08月20日(日)付熊本日日新聞朝刊掲載